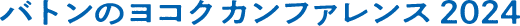Report
このイベントは終了しました
PASS THE BATON
CONFERENCE 2024 REPORT

日時:2024年10月10日(木) - 11日(日)
会場:コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」
主催:バトンのヨコク(コクヨ株式会社 / PASS THE BATON)
「地域課題」の根っこに、ユニークネスのヒントがある?
地域課題解決の伴走ユニット「バトンのヨコク」による、「バトンのヨコクカンファレンス2024」が2024年10月10日(木) – 11日(金)コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」にて開かれ、2日間の開催のうち、自治体担当者や民間事業者、学生や有識者ら811名が来場しました。
「地方創生」や「地域課題解決」、「官民共創」などの言葉は一般化しつつありますが、各地のプロジェクト事例を集めて、そこに関心を寄せる人々が等身大の言葉で直接対話ができる機会は、まだまだそう多くはありません。このカンファレンスでは、自治体、民間企業、学生や有識者が情報収集・活動発信・意見交換ができる学びの場として開かれました。このレポートでは、カンファレンスの当日の模様をダイジェストとしてお届けします。
Index
市長と課長の本音にハッとして。
「共創」実践者たちのリアリティ
品川駅から徒歩数分、まちに開かれたコクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」の入り口へ、続々と来場者が集結。受付で名札代わりの「ジモトカード」に、地域やジモトへの思いや課題を記入し、2Fのカンファレンス会場へ向かっていきます。


1日日の基調講演は「話題の公共施設・おにクルの仕掛け人&市長に訊く! 地域の共創実現」と題して、大阪府茨木市の福岡市長、共創推進課 課長の向田さんを迎えました。カンファレンス会場がほぼ満員となる、あふれんばかりの熱気。トークが始まる前から、その期待値の高さがうかがえました。
文化・子育て複合施設「おにクル」は、開館から287日目となる2024年9月8日(金)に、来館者数が150 万人突破。市長の考える、首長や行政の役割、開館に向けたプロジェクトの経緯、担当者の向田さんが市長に投げかけられた「問い」についてなど、具体的でリアリティの詰まった、エピソードを盛り込みながら開館の意図、プロセス、開館後も続く、場づくりの試行錯誤を語っていただきました。


基調講演に続く形で、登壇者への質疑応答を聴講者が“記者のように”行える、記者会見風セッション「貴重な記者体験」を実施。プロジェクトの担当者である向田さんから、「実務者」ならではの苦労や課題の乗り越え方などを、熱心に30分かけてお答えいただきました。質問者の方も、自治体の「実務者」であったり、事業会社で「地域密着」を模索されている方だからこそ、本音が飛び交います。実践者同士の対話は、言葉の一つひとつにしっかりとした重みがあり、聴講者の深いうなずきや、びっしりとメモを取られる姿が多くみられました。


昼の休憩時間には1Fの展示も大変盛況に。「空想旅行代理店」では、1000以上の地域紹介パンフレットから32種までに厳選したものを「きもち」のカテゴリにわけて展示。来場者がその日の「きもち」に合わせて、気になるキャッチコピーが書かれた封筒を手に取り、地域との新たな出会いを体験しました。
ある市の担当者は全種類をお持ち帰り。「封筒に書かれたキャッチコピーを読んだら、もうどれも気になってしまって!まんまと持ち帰らせていただきます」。もともとのパンフレットから、ユニークネスを抽出し、それに新たに言葉を添える。その見立てだけで、地域との新たな出会いをもたらすことが叶いました。


午後は、マガジンハウスのウェブマガジン「コロカル」編集長の山尾さんと、地域創生事業に注力する「日本旅行」執行役員の吉田さんのセッション「地域の魅力をどう編集する? Colocal、日本旅行に聞く、地域の見立て」が引き続き大盛況。このセッションでは、メディアと旅行会社というそれぞれの立場から、地域に眠る「価値の源泉」をどう発掘し、編集し、届けているかの具体的な事例やポイントが語られました。


このあとも、立教大学コミュニティ政策学部の学生によるピッチ、「『米惣動』からはじまる、地域の農と食のブランディング―」や、「地域プレイヤー×NTT東日本。「通い農」から創る社会ムーブメント」といったテーマで、「共創」という言葉をときほぐすような時間に。
セッションのあとは、1Fで「大名刺交換会」。任意参加の交流会を実施しました。立場の異なる聴講者同士が語り合える場となっており、まちづくりを学ぶ学生と自治体職員の対話、地域課題解決の選出事例の担当者が北海道から参加し民間事業者と具体的なディスカッションを行うなど、リアルの場だからこそ成せるコミュニケーションが場内で多数生まれました。入場時に配布したジモトカードも、会話の手立てとなりました。


主語はだれか。課題はなにか。
視点の置き方で本質が見えてくる
2日目は、朝一番に2日間連続で参加する自治体担当者の姿も見られました。全国各地からの参加、セッション開始前から1F展示がにぎわいました。


1日目の基調講演は自治体発信だったので、2日目は民間の取り組みを中心としたプレゼンテーションとなりました。まちに開けた「喫茶ランドリー」を主宰する田中元子さんの一声が、会場内にとても大きなインパクトを残しました。「日常生活をしている時は、“自分は何が好きか”“自分が何をしたいか”って考えているはずなのに、いざ、スーツをきたら、“自分”が本当は何をしたいのか?というところが抜け落ちていってしまうのってなんでなのかしら、と私は思うんです」。まちのにぎわいは、作るものでなく、結果的に作られるもの。大きな主語でなく、まずは自分を主語にして、スモールスタートで実践をしていくことの重要性を、自らの実践例を通して話してくださいました。


午後からのピッチでは、女川町商工会や能登の復興に取り組む日本航空の有志ユニットなど、民間での地域プレイヤーたちが集合。震災復興の観点、食を通じた地域の魅力発信、流通の展望など、現在地も含めたプレゼンテーションを展開しました。


2日目のトピックとして取り扱われたのは「地域とデザイン」。デザイン政策の先進国のひとつである台湾の政府系シンクタンク「台湾デザイン研究院」副院長・艾淑婷さんに、地方自治体におけるデザインセンターの役割や、伝統工芸・地域産業のデザインを通じた振興事例を伺いました。
最後のセッションでは、山形県の老舗スーパー「エンドー」さんとその伴走者であるデザイン事務所「杉の下意匠室」のお二人を迎えて、「山形の老舗スーパーがグッドデザイン賞をとるまで」と題して、地域のお客さんとの実直な向き合い方、デザインによる後押しをひもとくセッションを展開。山形を感じるリラックスしたのびやかな空気感、地域産業の本質的な価値づくりのあり様を会場全体に共有いただきました。


すべてのセッションが終了し、聴講者は1Fのメイン展示と大名刺交換会へ移動。メイン展示「地域課題のピントとヒント展」は全国の地域課題解決実践の130事例の中から、20選を選出しました。「課題設定」に着目をしたこの展示では、実際にその取り組みを行う自治体担当者や事業者の方が、自ら解説される姿も。




I'm Your Home./青空留学/安芸の島の実プロジェクト/an and an/いきつけいなか/稲作ほしの/駅前リビング/北の屋台/さがデザイン/シオクリビト/JAPAN MADE PROJECT TOHOKU/スナック水中/デデデデデンサン/農家の刺客/PLUG MAGAZINE/防災テーマパーク宣言/村ガチャ/レールマウンテンバイク Gattan Go!!/出展:中川町 など、全20事例をご紹介しました。
大名刺交換会では、セッションやピッチ登壇者がプレゼンの中でも触れた、地域の価値向上を目指した産品、プロジェクトで生まれた商品を、実際にその場で振舞う一幕も。話を聞いて終わりでなく、実際に飲食することで、より深い理解につなげていく。そうした瞬間そのものが、来場者同士の会話のきっかけとなりました。




「たくさん名刺を持ってきたはずなのになくなってしまいました!(笑)」という声も聴かれるほど、大盛況となった大名刺交換会。両日参加をした来場者同士の積極的な交流や、ジモトカードで同じ地域出身者をみつけて声をかけあうシーンなどもみられました。名刺交換は、ひとつの入り口。自治体、民間事業者、教育関係者、学生など、それぞれの立場で地域を向きあう一人ひとりの「交点」として、バトンのヨコクカンファレンス2024はその幕を閉じました。次回の開催は、2025年秋を予定しています。(終)
協賛社
協力企業
参加自治体
〈参加〉
- 青森県東京事務所
- 宮城県女川町
- 福島県只見線管理事務所
- 栃木県宇都宮市
- 群馬県太田市
- 三重県鳥羽市
- 大阪府池田市
- 奈良県明日香村
- 山口県山口市
- 徳島県
- 長崎県小値賀町
- 大分県別府市
- ほか
〈出展〉
- 北海道中川町
- 岡山県真庭市
- 佐賀県